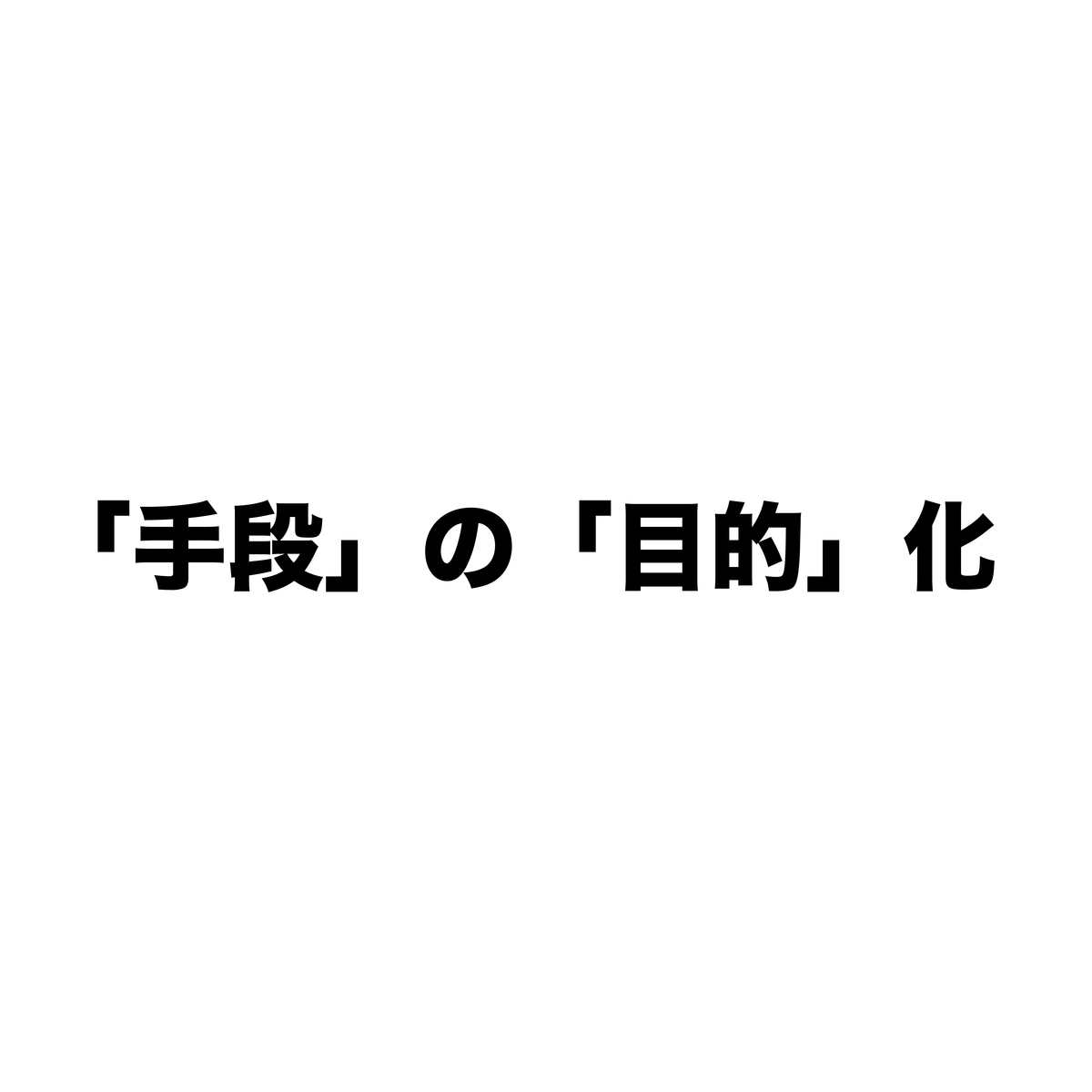 先日、ふとしたきっかけで、タイトルにある問題について考える機会がありました。
先日、ふとしたきっかけで、タイトルにある問題について考える機会がありました。
大学生の時に考えたことがあった問題だったのですが、ここ最近、自分の身の回りではこうした問題が生じなかったので頭の中の奥底で眠っていたのですが、前述のとおり、ふとしたきっかけで思い出し、考えるに行ったのです。
予め申し上げておきますが、特定の人を批判したり侮辱する意図は全くありません。
あくまでも陥りやすい罠とそうならないための注意喚起を促す趣旨の記事になります。
きっかけ
タイトルの問題について書く前に、先に述べた「ふとしたきっかけ」について書こうと思います。
契機1
まず1つ目の契機は、過日、Twitter上でも話題になった以下のツイートです。
「勉強が楽しい」という子を見ると、あぁこの子はまだそこまで勉強してないんだろうなぁと思う
— 山口真由オフィシャル (@mayuyamaguchi76) 2022年3月22日
1日19時間半勉強したときは、むしろ苦痛でしかなかったし
で、そのうち、この苦痛にこそ生きてる実感を覚えるくらいに疲弊してきて、そこまでいけば急速に解脱に向かうのだという気がする
このツイートに対しては、リプ欄に批判的な意見が多く寄せられていましたが、僕自身はちょっと別の見方をしております。
それに関しては後述します。
契機2
先日、とある方のツイキャスを聴いていて、こんな発言がされていました。
この発言を受けて、改められて考えさせられたのです。その発言とは
- ◯◯先生の講義を聴きたい
- ◯◯先生が解説してくれたらいいな
といったものでした。
その◯◯先生に対する敬意や謝意というものは特に何とも思っていないのですが、もし、いまだに依存しているような意識があるのであれば、ちょっと気をつけたほうが良いのではないかと思った次第です。
「手段」が「目的」化してしまう
さて、勉強をしていると陥りやすいのが、「手段」が「目的」化してしまうことではないでしょうか。
わかりやすい例を挙げると、ノート作りをする勉強法です。テキストをまとめたり、書き写したりするいわゆる「ノート作り」は膨大な時間を要することに加え、ノートを作ることが目的になってしまいがちなのです。

小中学校までの勉強であれば、この方法でも定期テストで点をとることはできますが、高校以上や資格試験となるとこの方法では厳しくなります。時間対効果に見合わないからです。そんなことをしている暇があったら、過去問を何度も繰り返して、必要な知識を叩き込んでいく方が遥かに効率が良いです。
ノートを作るにしても、自分が苦手なものだったり、何度も見直したい部分など、弱点だけを集めたものを作る程度に留めておくのがよいでしょう。
話が脱線し始めました。本稿はノート作りがテーマではないので、ノートに関する話はこの程度にしておきます。
上述の契機1でとりあげたツイートに関して、別の見方をしていると書きましたが、僕は「勉強が楽しい」ということは下のツイートに記載した通りではないかと考えています。
楽しく感じるのは、それが「目的」になってるからだと思う。苦痛なのは、「手段」だからだと思う。つまり、試験に合格するための「手段」としての勉強だからじゃないですかね。
— てぃーし/予備試験勉強垢 (@tidus_studylog) 2022年3月22日
勉強すること自体が目的なので、楽しいと感じるのでしょう。ただ、これが「◯◯のための勉強」という手段になると、ちょっと毛色が変わってくると思います。
 また、契機2の方に関しては、人気講師と受講生との間に生じやすい問題ではないでしょうか。
また、契機2の方に関しては、人気講師と受講生との間に生じやすい問題ではないでしょうか。
なぜ、その講義を聴くのでしょうか?
合格するためですよね?
つまり、合格することや点数がとれるようになるための手段として講義を聴くのであって、その講師の講義が聴きたい、その講師の講座を受講したいという欲求から、講義を聴くこと自体が目的になってませんでしょうか?
そして、最悪なパターンは、不合格になった際に「また◯◯先生の講座が受けられる」と思ってしまうことです。まあそんな人は極めて稀だと思いますが。
もっとも、学問的な欲求を満たすために講義を聴きたいと思うことは否定しません。試験とは離れますし、純粋に「知りたい」「学びたい」という想いから講義を聴くわけですから、その「欲求」(=目的)を満たすための「手段」として講義を聴くわけですから。
防止策
 では、どうしたら「手段」の「目的」化を防止できるでしょうか。
では、どうしたら「手段」の「目的」化を防止できるでしょうか。
これは、私見なのですが、その行動を行う前に「なぜやるのか?」という理由を考えてみるのが良いかと思います。
「手段」が「目的」化してしまう顕著なケースは「どうやってやるのか?」という方法論を考えてしまうことでしょう。
理由を考えみることで、目的が明確になりますので、少なくとも着手時点での「手段」の「目的」化は防止できるでしょう。ただし、人間は行動を続けているうちに、気がついたら「手段」が「目的」化してしまうという場合もありますので、定期的に「なぜこれをやっているのか?」を振り返ってみることが肝要かと思います。
最後に
以上、受験生が陥りやすい罠、「手段」の「目的」化について書かせて頂きました。重ねて付言しておきますが、本稿は特定の誰かを批判など攻撃する意図は全くなく、あくまでも注意喚起が目的です。
偉そうなことを書いてきましたが、僕自身も時々陥ってしまうことがあるので、定期的に振り返って軌道修正するようにしています。
例えば、論文試験の勉強です。論文試験の勉強として、論文答案を書いておりますが、毎日毎日書いていると、答案を書くことが目的になってしまい、なぜ書いているのかを忘却しがちになります。
そんなわけで自分への戒めとしても、本稿を書いた次第です。
「受験生が陥りやすい罠」と書きましたが、実はこれ、ビジネスでも起こりやすいので要注意です。
例えば、M&Aを例にとって紹介しますと、会社や事業を買うことが「目的」となってしまい、どうしてその会社や事業を買うのか、その理由が置いてけぼりになってしまうことがあり得ます。そうなると会社を買ったはいいけれど、全くシナジーなど生まれるはずもなく、経営のお荷物になったり、のれんや株式の減損処理を行わなければならないといった事態になってしまいます。
昨今、事業承継が問題となっていて、M&Aのコンサル会社や仲介会社、あるいは仲介サービスが増えてきているので、こうした事態に陥りやすいといえます。流行りに乗って「会社を買おう」と思っている方は、「なぜその会社を買うのか?」を考えてみた方が良いかと思います。
本稿を最後まで読んでいただきましてありがとうございました。
それでは!